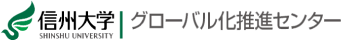言語の壁を越えて:アメリカでの成長記録
前澤 慶次郎さん
工学部 電子情報システム工学科
留学期間:2024年9月~2025年6月
留学先:南オレゴン大学
留学先大学について
南オレゴン大学は、アメリカ・オレゴン州の南部にあるAshlandという人口約2万人ほどの小さな町に位置する公立大学です。総生徒数は5,400人ほどであり、キャンパスもアメリカの他の大学と比べるとかなり小さい規模の大学です。しかし、41種類もの専攻学位プログラムが提供されているほか、小規模ゆえに教授1人に対して10~20人ほどの生徒数という少人数での授業形態を実現することができ、生徒同士や教授との距離が近く、気軽に質問したり討論したりできる学習環境が整っています。スポーツも盛んであり、NAIA(全米インターカレッジ・アスレチック協会)に所属し、数々の種目で輝かしい成績を残しています。学生の割合は、白人系が大半を占め、ヒスパニック系や黒人系、アジア系の人種はかなり少数になっています。様々な国からの留学生を受け入れているので、年によっては様々な文化を背景に持つ方々と関わることができます。また、現地の学生含め教授たちはもちろんのこと、Ashlandに住む住民もみんな親切で穏やかな方ばかりで治安も良いため、留学期間中は安心して生活することができました。


学習面について
私は主にコンピュータサイエンス系の授業を履修していました。どの分野でも共通事項として、基本的に1つのクラスに対して週2コマの授業があります。(一部例外あり)コンピュータサイエンス分野の授業は日本の授業形態と非常に似ており、週の1コマ目は講義で2コマ目は演習という流れでした。私が実際に受講していた「Network Security」という授業を例に説明すると、火曜日は教授の講義をひたすら聞いて、木曜日に講義で学習した範囲の知識を用いて、実際にWiFiルーターやSwitchなどの通信機器の設定を行うというようなものでした。この授業は計7名ほどの少人数のクラスであったので、クラスメイトはもちろんのこと、教授とさえも友達のような感覚で接することができました。そのため、分からない事があれば互いに質問し合い、問題を解決していくことができ、この一連の流れがまさに知識を知識だけで終わらせずに、それを用いて技術を身につける実践的な授業であると感じ、コミュニケーション能力や無線通信分野の技術力など様々な面で成長できた学習環境でした。コンピュータサイエンス系の授業の毎週の課題としては、演習内容で達成したことやあらかじめ教授から与えられる質問への回答をまとめたレポートを提出することと、基礎事項を抑えたオンラインクイズでした。あまり分量は多くないといった印象です。
その他にも私は、美術の授業や音楽史の授業を取っていました。美術の授業は、版画や石膏、彫刻など様々な分野がありますが、美術の授業を取った現地の学生の友達の声と私の意見を基に判断すると、課題内容が結構大変です。私は版画の授業を取っていましたが、10週間の間に3つの作品を作り上げるため、ほぼ毎週何かしらのスケッチや作品制作に追われていました。
音楽史の授業は、アメリカのRock Musicの歴史について学ぶ授業で、大きな講堂で実際にRock Musicを聞きながら教授の講義を聞いたり、周りの学生と議論するようなまさにアメリカらしい授業でした。課題自体はとても簡単な内容のレポートを1ページ以内で済ませるものだったので、肩の力を抜いて受けることができるものでした。
専攻に依りますが、友達の話を聞く限り多くの専攻の授業では、グループディスカッションやグループプロジェクト、グループプレゼンテーションなどが頻繁に行われるようです。私が受講した美術の授業でも、作品を完成させたのち、みんなの前で自身の作品のイメージやコンセプトを説明したり、他者の作品について批評するなど、みんなの前で発言をするという機会は多々ありました。特定の専門分野について自身の意見を英語で表現することは非常に大変でしたが、学生含め教授たちがサポートしてくれるので安心して発言することができました。
また、予習の段階でかなりの量のページを読んでくることを要求される授業もあるそうです。例として、歴史学を専攻しているアメリカ人の友達は、週に多いときは計200ページもの読み物が予習として与えられることがあり、ネイティブスピーカーの彼でさえとても苦労しているようでした。
中間・期末試験の有無は授業によって左右されます。試験前は図書館の利用時間が伸びたり、友達間でも遊ぶことを控えたりと、普段とは違い大学内の空気感が真面目に勉強するものへと変化します。図書館以外にも、寮内には勉強スペースがあったり、そのほかの施設でも勉強はできるスペースは確保されているので、学習環境はかなり整っているほうだと思います。

生活について
大学から徒歩5分圏内にオーガニック系の食料品スーパーがあります。ただ、このスーパーはその他のスーパーと比べると値段が高いので、比較的安いスーパーを求めるのであれば、Ashlandのダウンタウンまで行くと全国規模のスーパーマーケットチェーンであるSafewayがあります。ダウンタウンまでは片道2ドルで利用できるバスを使うか、徒歩で2.5kmほど歩く必要がありますが、平坦な道で尚且つ町の治安が良いので早朝や夕方でも1人で外を出歩いて全く問題ありません。
同じく大学から徒歩5分圏内にはアメリカ版の100円ショップであるDollor Treeや大手ハンバーガーチェーンのWendy's、そしてローカルな飲食店が少しあります。Ashlandのダウンタウンにも雑貨店や飲食店は多くあるので、基本的に生活面で困ったことはありません。
現地の学生は基本的にみんな車を持っているので、彼らに運転してもらったり、バスを使って隣町のメドフォードに行くと、そこには大手スーパーマーケットチェーンのWalmartやTarget、大手バーガーチェーンのMcDonaldやBager King、Chick fil A、ローカルなレストランや映画館、そして日本企業のDAISOもあるので、必要なものは手軽に手に入る環境でした。
留学生は基本的に大学の寮に住むことになります。私が選択した部屋は、1つのリビングルームと2つの寝室がある部屋です。それぞれの寝室では仕切りなしの空間にベッドと勉強デスクが配置され、最大2人が暮らすことを想定した造りになっています。バスルームは各寝室に1つずつなので、基本的には同部屋の2人でバスルームをシェアする必要があります。他にも部屋の種類や寮の種類なども選ぶことはできますが、金額がそれぞれで異なります。
食事面についてですが、朝昼晩の3食は基本的に学内の食堂で済ませていました。食堂で提供される食事は基本的に揚げ物やハンバーガーやピザが圧倒的に多く、生野菜やヘルシーな食事は摂取しずらいので健康的な食生活を維持することが難しかったです。しかし、大学内の施設としてジムが無料で使えるのでそこで運動したり、毎週2、3回だけ友人たちとバレーボールをしたりすることができたので、健康で充実した生活を送ることができました。
娯楽施設として、E-sportsルームというゲーミングPCが10台ほど完備された部屋があったり、PS5やXbox、Nintendo Switchが自由に使用できる場所もあります。また、ビリヤードや卓球などが遊べるゲームルームもあり、授業の合間や夕食の後など友達と利用して、とても楽しい時間を過ごすことができていました。
最後に、長期休みについてですがアメリカではほとんどの大学で冬休み期間中(約1ヶ月間)は寮が閉鎖されてしまいます。南オレゴン大学では、冬休み期間中に宿の提供はありますが有料でかなり限りがありました。私はその期間を使って、サンフランシスコやシアトル、ロサンゼルス、ニューヨーク、ラスベガス、グランドキャニオンなどアメリカ国内の観光地を友達と旅することにしました。補足ですが、交換留学生でも学生証を持っているとアメリカ国内の美術館や博物館は学割を使っては入れるのでお得です!私は、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館に訪れた際、学割を使うことで通常価格より$13も節約して入場することができました。

留学で得たこと
留学で得たことは異文化適応力やコミュニケーション能力の向上などたくさんありますが、私にとって最も大きな収穫は挑戦することを恐れなくなったことです。正直に言ってしまえば、私はプライドがとても高く、失敗することを恐れるがあまり挑戦することを可能な限り避け、現状維持を基本とし、与えられたチャンスのみ物にすることを考えてしました。実際に渡米した当初は、自身の英語力が周りに比べて非常に低いことを実感したにも関わらず、無駄に高いプライドによって能力の低い人に見られたくない気持ちが勝り、英語で他の留学生や現地の学生とコミュニケーションを取る際には翻訳機を使って文章を考える機会が多々ありました。しかし、それでは円滑なコミュニケーションが取れずに自身の成長の妨げになっていることを自覚し、ある日、文法がめちゃくちゃで単語も適切ではないかもしれないけれど、自分がその時に持っている英語力で勝負しようと決め、コミュニケーションを取ってみると、私の置かれている環境では嘲笑したり見限る人は一人もおらず、むしろそんな私と真摯に向き合ってくれる人たちばかりであったことに気が付けました。この環境に背中を後押ししてもらい、その日からはいくら時間をかけても、どれだけ文法がおかしくても自分の持っている英語力で意見を伝えようとする挑戦をし続けました。その結果、リスニングやスピーキング能力が大幅に向上し、ネイティブスピーカーとも対等に話せるまでに成長することができました。
この出来事が自信となり、その後は、いろいろなコミュニティの方々に恐れることなく話しかけて、知り合えたり、仲良くなれたりし、時にはうまくいかないこともありましたが、以前とは違い、「挑戦をした」という事実に価値を感じれるようになったので、うまくいかなかったことでもポジティブに捉えることができるようになりました。
この経験は、私の将来に必ず役立つと確信しています。

後輩へのアドバイス
留学をすることは、きっとあなたにとっても大きな決断になるはずです。私もそうでした。そして、留学をするにあたっては様々な事項について考えなければなりません。例えば、信州大学での授業履修や卒業時期はどうなるのかについて、就職活動はどうするのか、留学資金の確保など... それらを踏まえたうえで留学に行くことが本当に最適な選択なのかは誰にもわかりません。私自身も、留学することで私の人生にプラスになるのか否かについては、留学前の段階では分かりませんでした。ただ、"日本から飛び出してみたい"という思いがありました。そんな単純な動機でしたが、結果として留学は私の人生にとって非常に良い経験となりました。
だからこそ、迷いや不安があっても、まずは一歩を踏み出してみることに価値があると思います。留学は勇気のいる決断ですが、その一歩が、きっとあなた自身の世界を広げてくれるはずです。自分の可能性を信じて、ぜひ挑戦してみてください。
留学に関して相談したいことや心配事があれば、グローバル化推進センターを通じて連絡をください。
知の森基金へのメッセージ
信州大学 知の森基金を支給していただき誠にありがとうございました。30万円程を支給していただき、全額を往復の航空券代に充てることができとても助かりました。この貴重な留学の経験をするにあたって支援してくださった知の森基金には多大なる感謝を改めて申し上げます。